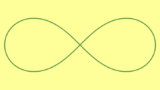前回、修士論文の発表で散々批判された話を書いた。しかし、その少し前には遥かに酷い修士論文が許されていた。その頃は修士課程の入学に筆記試験がなく、指導教員が受け入れを認めれば合格となっていた。修士課程の定員を満たすことについて文科省の締め付けが厳しく、学部生の多くに進学してもらわなければならない。推薦のない学生は合格が保証されない。不合格の後に就職は厳しくなるから進学しないという学生は多かった。そこで、筆記試験を廃止して希望者は確実に進学できるようにした。学外からの受験者をどうするか。文科省の指導に従えば、学内外で基準に差をつけられないようである。本学の卒業生なら学力について最低限の期待はできるが、学外からの受験者をどのように評価するか。学外からの受験者だけ筆記試験を課すわけにはいかない。最終的には受け入れ教員に任せる方針となった。無試験になる前から響研に中国人の希望者があったが、筆記試験に合格しなければならなかった。無試験になってからは素養の無い学生も合格するようになった。中国での専門が英語や体育など理系の教育を受けていない事例が生じた。本来なら響教授が受け入れを拒否すべきだった。入学後も指導はしないし、学習状況も確認しない。もっとも、これは留学生に限らないが、IT教育を受けていない留学生にとっては酷い結果となる。特に酷かった修論の事例をあげる。彼は Java をそれなりに修得し、修論のテーマは中国語で入力できるお絵かきソフトの作成だった。発表時に実装されていたのは円と線分のみで、機能を増やすのが今後の課題とされた。公聴会に出席しているのは、主査の響教授、副査の准教授2名、響研の助教である私だった。同時に複数のセッションが実施されていて、そこで審査している教員は参加できない。空いている教員もどこかのセッションに出席する義務はなかったので、関係者以外出席することはなかった。2セッションで出席義務が課されるようになったのは後の事である。響教授は反対することのない准教授を副査に指名していたので、なんら否定的な発言をする者はいなかった。当然であるが、内心不愉快な副査もいた。響教授には文句を言えないから矛先は私に向く。響先生に直接言えばと言っても、響先生の問題ではなく、お前の責任だと非難し続けるのだ。響教授には、せめて理系出身でない留学生を受け入れるのを止めて欲しいと申し上げたが、断るわけにはいかんと怒鳴りつけられて終わった。受け入れるなら責任をもって指導し、できないのであれば受け入れを断るべきだと、個人的には考える。研究は自己責任として指導は放棄していた。それは日本人学生に対しても同じだった。ただし、どんな内容でも修論として認めた。副査には異論を許さなかった。留年を出すと研究室の評価が下がるというのが理由だった。私には理解できなかった。どこからの評価を気にしているのだろうか。こんな修論を認めている方が評価が下がるように思う。しばらくして筆記試験が復活した。響研の修論が直接関係しているわけではなかったが、最低限の基礎学力はチェックしたいと思ったようだ。
中国人留学生
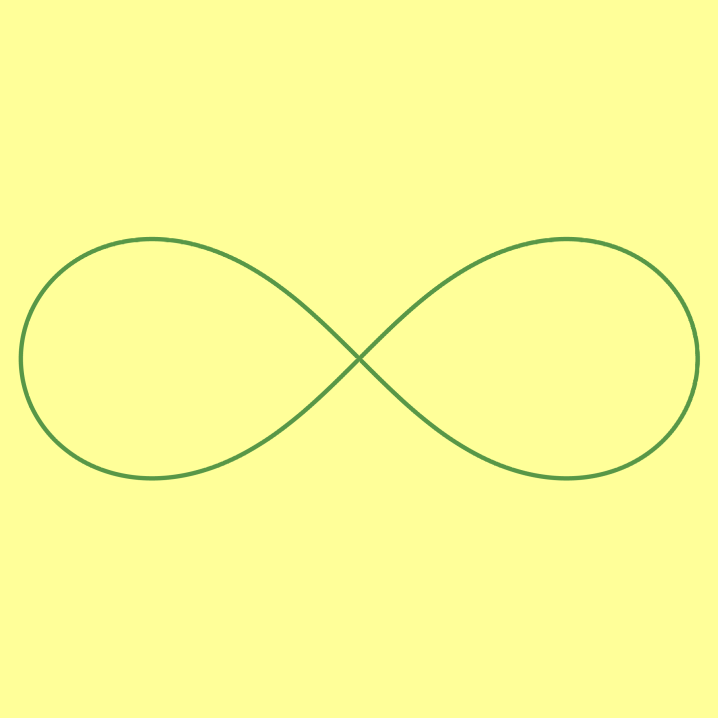 教員生活
教員生活