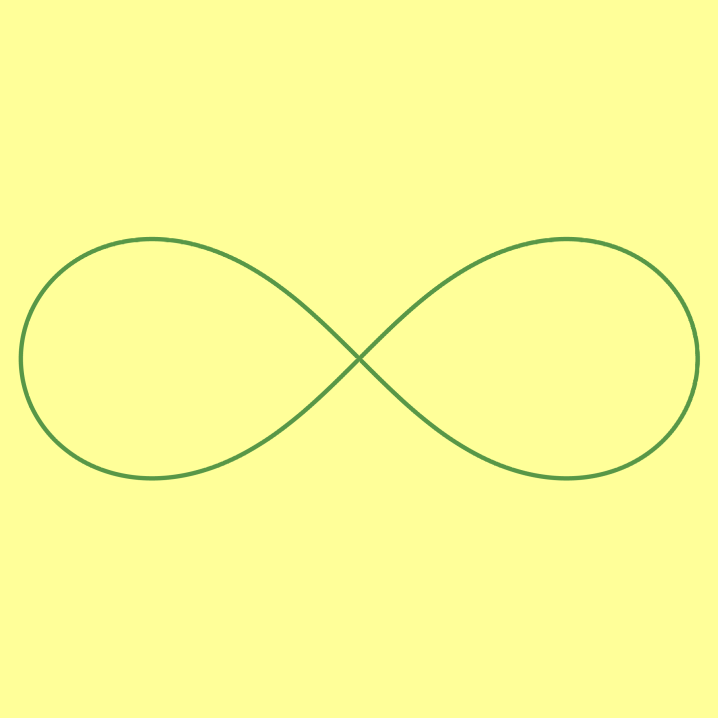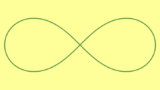前回の続きで、OSの移植をしていた学生の修士論文はどうなったのかという話である。企業から外部資金を得ている場合、企業の要求に答えつつ如何に研究テーマに結び付けていくかは指導教員にとって悩ましい所である。移植は研究とは言えず、早く完了して何らかの新規性を追加する必要があるが、学生の進捗状況はそれどころではなかった。この指導体制では遅々として進まないのは仕方がない。修論のテーマはどうするのだろうか。移植がテーマになってしまうのか。
学生がM2の時には准教授に昇進して研究室を離れていた。修論発表会の題目が出てきた。題目には移植の先まで含まれていた。移植は終わったのだろうか。学生の所に行って聞いた。
「移植ですらこれだけ手間取っているのに、ここまで出来るの?」
「響先生が移植だけじゃ弱いって言うから。」
移植は研究とは言えない。実習の範疇だ。しかし、出来もしない題目を掲げても、心証を悪くするだけではないか。正直に移植を題目にした方が、先入観で審査員も妥協してくれるかもしれない。
発表当日、2教授が徹底的に批判した。移植が大変なのは分かるが研究ではない。修士論文としては認められないと言わんばかりの激しい攻撃だった。発表後、学生は「響先生に申し訳ない」と言いながら台上で泣いていた。しかし、学生にこれ以上出来ることはなかったであろう。そもそもこれが限界の指導体制だった。響教授は学生の所に行って、「あいつらは何も分かっていない。気にすることはない。」と言って、学生を慰めると言うより、批判した2教授に対しての怒りを吐き捨てていた。響教授も2教授の批判は当然と理解していたからこそ、このような題目にしたはずではなかったのか。怒りは筋違いではないか。しかし、これまで研究科としてもっと酷い修士論文を許容しておきながら、今回の2教授の批判もどうなのかとも思う。修士論文が満たすべき条件は組織で共有すべきだと思う。